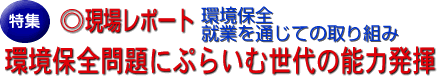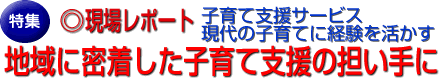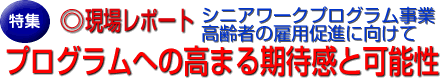|No.18| NO.19|NO.20 | NO.21|
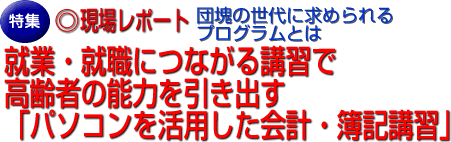 |
|
 |
|
| 分かりにくいところは講師が一人ひとり教えていく |
|
 |
団塊の世代が高齢者の仲間入りをする2007年。以後、ホワイトカラー層が増える中、企業のニーズに即した人材を育てるためのプログラムが問われている。1月に実施した講習を振り返りその方向性を探ってみた。 |
受講者は「技能を身につけ就業につなげたい」と、熱心に聞き入る
|
|
1月11日から18日の6日間、島根県シルバー人材センター連合会では企業側のニーズに即し、高齢者の就業・就職に照準を合わせた「パソコンを活用した簿記・会計講習」を開催した。最終日となる18日には松江ハローワーク・島根県経営者協会の協力、連合会主催で「合同面接会」の実施で受講者と企業側のマッチングも行った。 |
|
|特集 [取材/ぷらいむ提言/ぷらいむ知恵袋]|ぷらいむな人|ぷらいむROOM|
|しまねの散歩道|ふるさとの情景|いきいき暮らし健康情報|食べておいしい!健康メニュー|