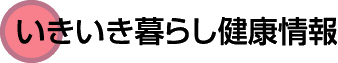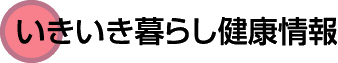「運動のすすめ」で、ウォーキングの大切さを19号のこのコラムで紹介しましたが、実践しておられますか? 皆さんの最も気になる症状は何でしょうか? 「国民生活基礎調査(2001年)」(厚生労働省)によると、第1位は、腰痛、第2位が肩こりだそうです。いずれも、約10人に1人の方がこういう症状をもっておられます。しかも、医者にかかっている人は、高血圧に次いで、第2位と第3位と高率です。腰痛や肩こりは、運動器の病気と言われますが、2000年から10年間かけてこういう病気を追放するための国際的なキャンペーンが行われています。
腰痛と肩こりは、どちらも2本足で歩くようになった人類の宿命と言われ、脊椎とそれをとりまく筋肉の疲労から起こります。皆さんは、どのような時にこの2つの症状が起こりますか? 「同じ姿勢を長時間続ける」「中腰の姿勢」「草むしり作業」「ストレスが続く」「運動不足」など原因となることがありませんか?
かっては、腰痛患者は「安静にしなさい」が定説でしたが、今は「動けるならば動きなさい」と整形外科の先生方も勧めています。腹筋や腰背筋を鍛えるストレッチや体操をゆっくりと無理のないようにすることが腰痛体操のコツです。もし、つま先立ちやかかとで立つことが出来ない場合は、できるだけ早く受診することが大切です。
肩こりには、筋肉のこりをほぐす体操やストレッチ、マッサージを無理せず、できるところまで曲げたり伸ばしたりすることを勧めます。しかし、四六時中、あるいは痛みが日々強くなる時は、医師を受診して下さい。皆さんの悩みの種の腰痛と肩こりを知恵と工夫で解消し、是非予防することをめざして下さい。 |